「不登校 親 しんどい」で検索された方は、疲れた心をどう守るか、どこまで頑張ればいいのか、高校生の対応やノイローゼに近い不調への向き合い方まで、具体的な答えを探していることでしょう。
母親ばかりが抱え込む現状を変えたいと感じるほど限界に近い時や、気が狂いそうな夜にどう耐えるか、メンタルの崩壊を防ぐための精神ケアや楽になる考え方、頼れる相談先を整理し、不登校でも大丈夫な理由もわかりやすくまとめます。
この記事では、疲れた時に読む短い指針として、今すぐ実践できる小さな一歩を提示します。
- しんどいサインの見極め方と初期対応がわかる
- 夜間の不安やパニック時の対処が身につく
- 高校生の選択肢と家庭の関わり方を理解できる
- 相談先の使い分けと頼り方のコツを把握できる
不登校の親がしんどい時の現実と対処
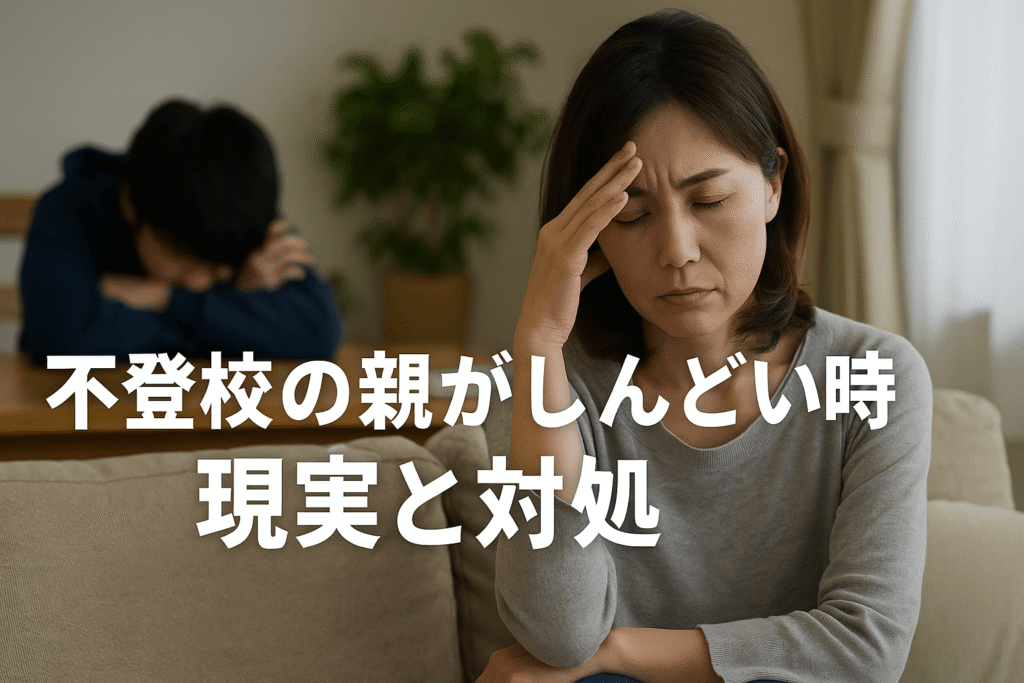
- 疲れた心のサインを見極める
- メンタル崩壊やノイローゼの兆し
- 気が狂いそうな夜の対処法
- 限界を迎える前に取る行動
- 精神ケアを日常に組み込む
疲れた心のサインを見極める
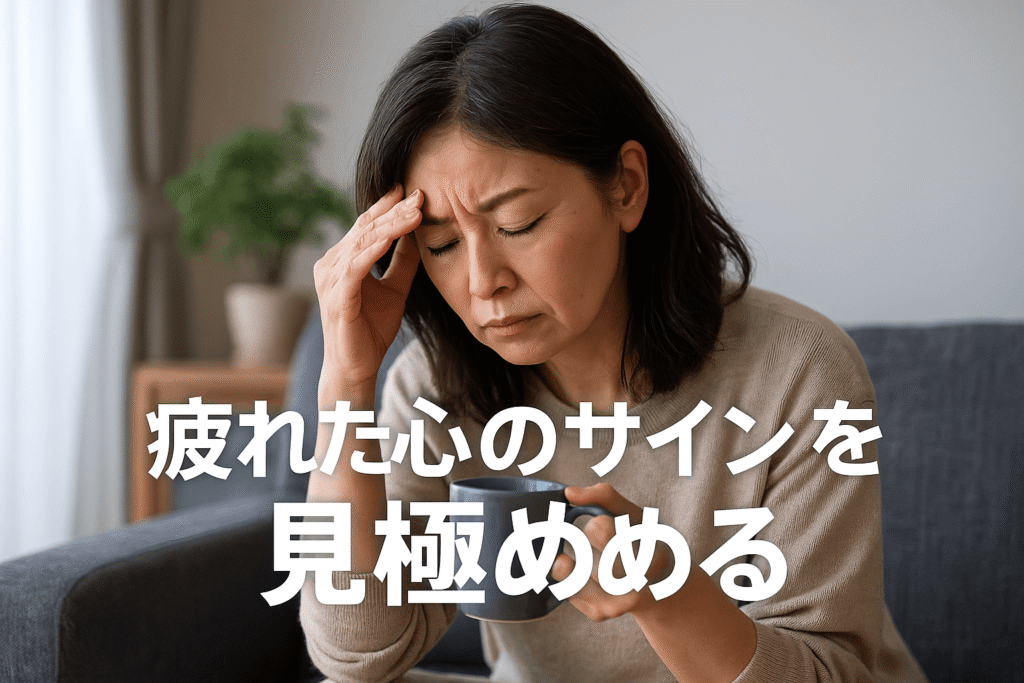
生活の細部に現れる小さな変化は、心身の負荷が限界へ向かっている合図となりやすく、以下のような症状はストレス反応が慢性化している可能性を示します。
- 朝の起床直後から体が重い
- 食欲のむらや胃腸の不快感がある
- 理由のない頭痛や肩こりがある
- 以前は楽しめた趣味への興味が低下する
思考面では、白黒で物事を決めつける極端化、被責思考の増加、先の想像がすべて悪い方向へ傾くことなどが増えていると、休息と環境調整の優先度を上げる必要があると捉えましょう。
行動面では、家事の段取りを組み立てにくい、学校や関係者に同じ説明を繰り返して強い疲労感を覚える、予定が詰まっているだけで胸がざわつく、といった軽度の実行機能低下が見られてきます。
これらが重なると回復に必要な時間が延びやすくなるため、以下のような対策が必要です。
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| 睡眠を固定する | 就寝・起床時刻の幅を±30分に収める |
| 決定の回数を減らす | 献立の固定化や服装の統一化 |
| 予定の上限を決める | 1日1イベント |
また、周囲に頼みにくいと感じる局面では、頼る行為を最小単位へ分解すると心の負担が軽減します。
1日のどこかで「5分だけ横になる」「湯船に10分浸かる」「ベランダに出て外気を吸う」「温かい飲み物を淹れる」といった短いセルフケアを決めて、実行できたらその場で終わりにすると良いでしょう。
メンタル崩壊やノイローゼの兆し

メンタル崩壊やノイローゼを未然に防ぐためにも、心身の過負荷が限界近くまで高まっているサインを把握しておくことが大切です。
- 情動の揺れが大きくなり
- 涙が止まらない
- 動悸や息切れ
- 手の震え
- 音や光への過敏さが出る
- 思考がまとまらず時間感覚を失いやすい
夜にひとり反省会が止まらずに「入眠困難」や「中途覚醒」が続く場合は、早期に専門家へ相談しましょう。
医療機関や公的相談窓口では、休養と生活リズムの再構築、必要に応じた治療や心理社会的支援の選択肢が段階的に案内されることが一般的です。
さらには、学校や行政との実務連絡は、一時的に第三者へ委任するだけでも負担軽減効果が見込めます。
なお、ストレスによる心身反応や対処の考え方は、公的機関による情報も参考にすると良いでしょう。(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~」 )
専門機関への受診・相談の目安
下記の症状ははいずれも、医療機関(かかりつけ、小児科、心療内科、精神科など)や公的窓口に相談する判断材料として用いられます。
- 眠れない日が続く、または極端に早く目が覚める
- 胃痛や頭痛が長引き、日常生活が回らない
- 希望のない気分が続き、自責が止まらない
- パニックに近い動悸や息切れが増えている
可能なら症状の期間、睡眠時間、食事量、仕事や家事への影響、困っている具体場面をメモして持参すると、短時間で実態が共有ができます。
学校や関係機関に提出が必要な場合は、診断書や意見書の発行可否や所要日数も合わせて確認しておくと、後の手戻りを避けられます。
精神状態が限界に近い状態では、移動や説明を聞くだけでも体力・集中力を消耗しやすいため、当日は「受診以外は休息」の一択にしておくと、回復の始まりが安定します。
気が狂いそうな夜の対処法
夜は不安・孤独・罪悪感が増幅しやすく、思考が極端に傾きがちです。
そこで、まずは以下の呼吸法をすることで、自律神経の興奮が落ち着いて体の緊張をほぐすことから始めましょう。
吐く時間を長めにする呼吸(4秒吸って6〜8秒吐く)を3〜5分、楽な姿勢で繰り返す
※顎・肩・背中の力を抜く意識を添えると効果が増す
次に、今できる行動を以下のように3つだけ紙に書きます。
- 温かい飲み物を飲む
- 5分ストレッチをする
- 暗い部屋から出て明るい場所へ移動する
- 常夜灯をつける
- 足湯をする
このように選択肢を可視化することで、頭の中の堂々巡りから距離を取りやすくなります。
また、音声メモを利用して不安を言語化する方法も効果的です。言葉として外に出すことで、感情のボリュームが下がり、入眠しやすくなるでしょう。
環境面では、寝室を「休むための部屋」に戻す工夫が役立ちます。
たとえば、ベッドで学校や仕事の連絡をしない、寝付けないときは20分程度で一度起きて別室で静かな読書や軽いストレッチに切り替えるなど、活動と休息をはっきり分けることで、脳が「ベッド=睡眠」と再学習しやすくなります。
限界を迎える前に取る行動

限界はある日突然訪れるものではなく、日々の小さなサインの積み重ねによって静かに近づいてきます。
気づかないうちに「頑張りすぎ」が常態化していることも多いため、意識的にブレーキをかける仕組みや心構えを持つことが、心身を守るためにも大切となります。
やめることリストで「しない勇気」を可視化する
家庭内の役割を一時的に見直し、やめることリストを作成することは有効です。
リストには「やらなくても困らないこと」「誰かに任せられること」「後回しにしても影響の少ないこと」を書き出します。例えば以下のように区分すると具体的に把握できます。
| 分類 | 内容例 | 代替策・工夫 |
|---|---|---|
| 家事 | 夕食は2品にする、掃除は週2回 | ・冷凍総菜や宅配弁当の利用 ・掃除ロボット導入 |
| 学校対応 | 朝の連絡を週2回は配偶者に交代 | ・メールでの共有 ・家族カレンダー連携 |
| 子育て | 毎日勉強を見ない | ・週末にまとめて確認 ・学習アプリの利用 |
このようにタスクを削減して、可視化しておくことにより「自分がどれだけの仕事を抱えているか」が明確になります。
特に育児と学校対応が重なる不登校期では、負担を見える化することがストレス軽減の鍵となります。
学校対応の省力化と記録の仕組みづくり
学校との連絡は感情的なやり取りになりやすく、精神的な消耗が大きい領域です。
そのため、連絡の頻度と手段を事前に取り決めておき「月1回の面談+メール連絡」に固定することで、予測不能なストレスを減らせます。
また、学校側に「家庭の状況を一度に共有できる書面」を渡しておくと、面談ごとの説明負担が軽くなります。これは行政が推奨する合理的配慮の一環としても有効とされています。(出典:文部科学省『不登校への対応について』 )
予防的ケアの視点を持つ
心身の疲労は、限界を超える前に緩やかに介入することで回復が早くなります。
週に1度「予定を入れない日」を設定し、何もしない時間を確保することは、単なる休息ではなく、心理的な余白を取り戻す行為です。
また、「誰かに話を聞いてもらうこと」も重要な予防ケアです。家庭外の人と話すだけで思考の整理が進み、ストレス耐性が上がるという研究もあります。
地域の相談窓口やカウンセリングサービスを定期的に活用し、セルフモニタリングを続けましょう。
精神ケアを日常に組み込む

精神ケアは、特別な儀式のようなものではなく、日々の生活の中で小さく積み重ねていくものです。
特に不登校の家庭では、子どものケアを優先するあまり親自身のケアが後回しになりがちですが、親の安定が家庭全体の安心に直結します。
朝のリズムを整えるセルフケア
朝に日光を浴びることは、体内時計のリセットとセロトニン分泌を促す効果があると報告されています。具体的には、起床後1時間以内に15〜30分程度、屋外や窓際で自然光を浴びるだけでも効果的です。
また、白湯や温かい飲み物を飲み、体温を上げることも自律神経を安定させる習慣として有効です。
これらに短時間のストレッチや15分程度の散歩を組み合わせると、1日の始まりに「心を整える時間」が生まれ、感情の波が穏やかになりやすいとされています。
感覚を使ったリラックス法
短時間で緊張を緩めたいときには、以下のような五感への刺激を使う方法が効果的です。
- アロマオイルや香り付きのハンドクリームを使う
- 好きな音楽を3分間聴く
- 温かいタオルで首を温める
さらに、夜の入眠前には「照明を落として深呼吸を3回し、日中の思考を切り替える」というルーティンを作ることによって、睡眠の質を安定させられます。
不登校の親がしんどいと感じたら今すべき事
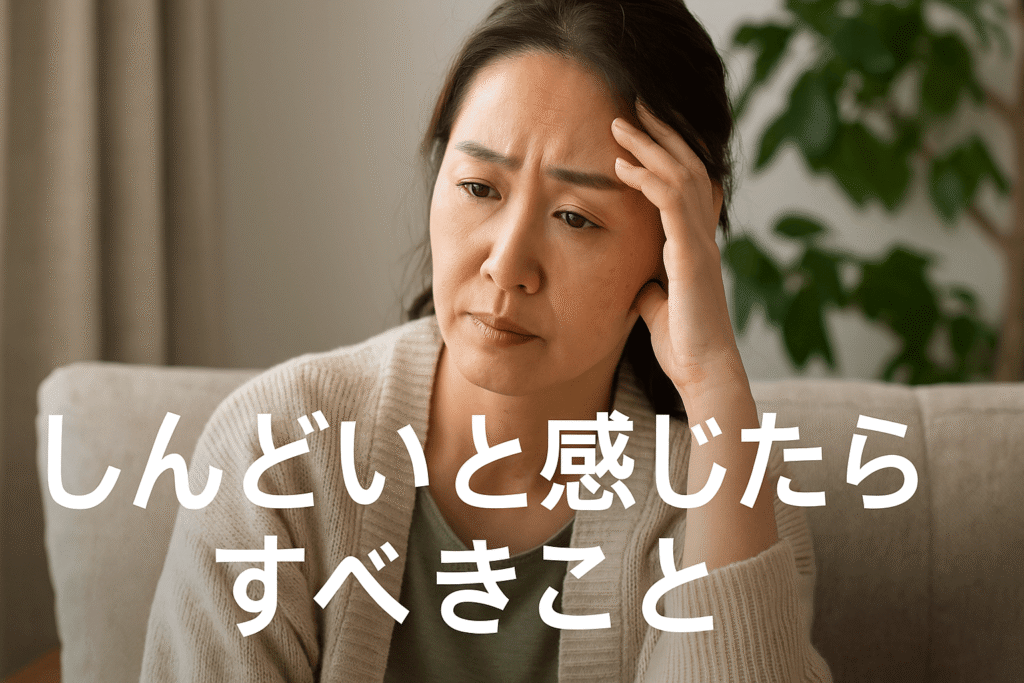
- 高校生のケースで見る対応
- 母親ばかりをやめたい時
- 楽になる考え方の具体例
- 相談先の選び方と活用法
- 不登校でも大丈夫な理由を整理
- 不登校の親がしんどい時は自分を守る
高校生のケースで見る対応
高校生の不登校は、進路や人間関係、将来への焦りなど多様な要因が絡むため、対応には柔軟性と時間が求められます。
まず、本人の体調と心理状態を確認し、「短期的な回復」と「長期的な進路」を分けて考えることが重要です。焦って一気に解決しようとするより、段階的に支援の道を描く方が効果的となります。
以下は代表的な学び方の比較表です。本人の性格・生活リズム・家族の支援体制を踏まえて、無理のないペースを選びましょう。
| 選択肢 | 通学頻度の目安 | 主な条件・学び方 | 向いている状況 |
|---|---|---|---|
| 全日制の継続 | 週5日が基本 | 校内支援・時間割調整・保健室登校の活用 | 学校支援を得て現環境での再適応を目指したい |
| 定時制 | 夕方〜夜中心 | 時間割が柔軟、少人数で落ち着いた環境 | 朝が苦手、生活リズムを整えたい |
| 通信制 | 月数回〜年数回登校 | レポート提出とスクーリングで単位取得 | 通学負荷を減らし学びを継続したい |
| 高卒認定 | 通学不要 | 科目合格で大学・専門学校受験資格を取得 | 学校外から進路を再構築したい |
通信制や高卒認定を経て大学や専門学校へ進学する学生は年々増加しており、文部科学省の調査でも学び直しルートとして制度的に整備が進んでいます。(出典:文部科学省「高等学校通信教育の現状について」。
母親ばかりをやめたい時
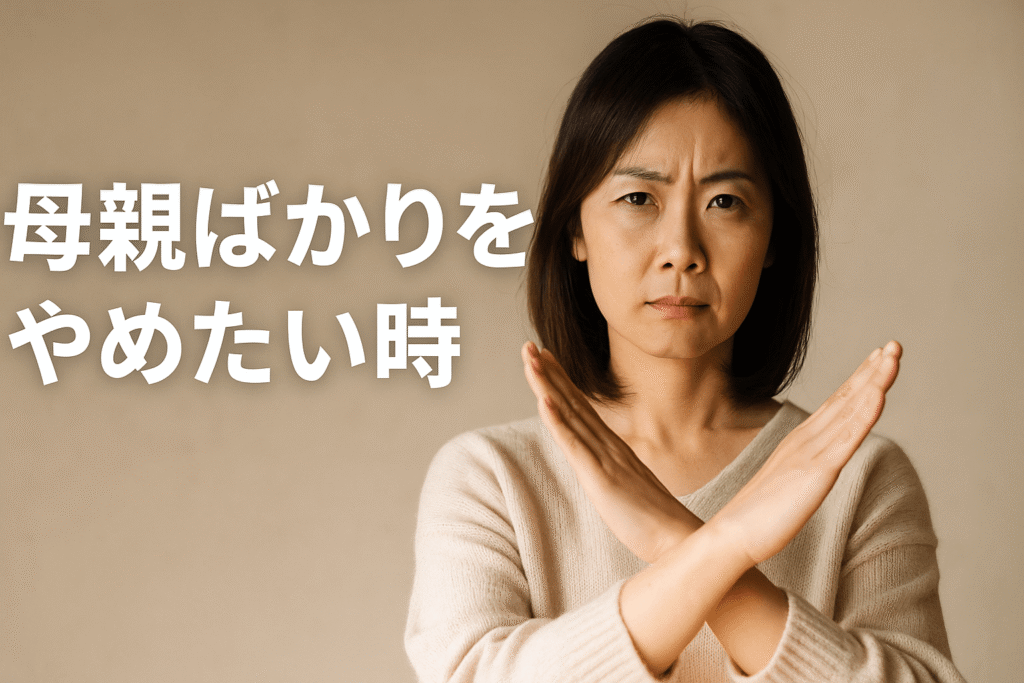
家庭の中で「母親ばかりが頑張っている」という状況は、多くの不登校家庭で共通する課題です。
学校や医療機関とのやり取り、家庭内のケア、家事、感情的サポートといった複数の役割を一人で担い続けると、肉体的にも精神的にも疲労が急速に蓄積してしまうでしょう。
そこで、家庭の安定を維持するためにも「すべてを母親が抱える」構造を見直し、負担を分担できる仕組みを意識的に作ることが必要です。
家庭内の役割を交代制にする
まず取り組みやすいのは、家事や通院、学校連絡などのタスクを週単位で交代制にすることです。
- 朝の学校連絡は週の前半を母親、後半を配偶者
- 通院の付き添いは月ごとに交代
- 買い出しや夕食準備は曜日ごとに担当を固定
このようにルールを明確化するだけでも「いつも自分ばかり」という心理的負担を減らせます。
分担を口頭で終わらせず、カレンダーアプリやホワイトボードで共有しておくと、家庭内の可視化が進み協力が得やすくなります。
家族会議を短く定期的に行う
頼みづらさを和らげるためには、家庭内のコミュニケーションを「感情の共有」から「タスクの共有」に切り替えることが効果的です。
週1回、10〜15分程度の家族ミーティングを設け、現状と来週の予定を確認します。その際は以下のように進めると効率的です。
- 各自の負担・困りごとを1つずつ共有する
- 来週の予定(学校対応・通院・家事)を確認する
- 「やめること」「他の人に頼むこと」を決める
この形式であれば、感情的な摩擦を避けつつ協力の仕組みを自然に作れます。家庭運営を「チーム作業」として捉え直すことが、母親一人に集中していた負担を分散させる鍵です。
外部支援を現実的に取り入れる
外部の力を借りることは決して怠けではなく、家庭機能を守るための合理的な選択です。家事代行や訪問型支援(ホームヘルパー、家事支援サービス)は、短時間からでも利用できて家庭の摩耗を防ぎます。
自治体によっては「子育て支援短期利用事業」や「家庭生活支援員派遣制度」など、費用の一部を公費で補助する制度もあるためチェックしておきましょう。(出典:こども家庭調「子育て世代包括支援センターの実施状況」)。
楽になる考え方の具体例
不登校という現象は、努力の欠如や育て方の失敗ではありません。今の環境が子どもの発達や特性に合わなかったという一つの事実にすぎず、親が過度に自責する必要もありません。
以下の見出しでは、気持ちを軽くしてくれる考え方の具体例を紹介していきます。
できていないことではなく、維持できていることに注目する
不登校の子を支える日々では、「できないこと」ばかりに目が向きがちです。しかし、「毎日食事を作れた」「声を荒げずに話せた」「今日は一緒にテレビを見た」など、維持できている習慣を見つめ直すことが、自己効力感を回復させる第一歩です。
心理学では、こうした「できていること」に焦点を当てる思考法を“リソース・オリエンテッド”と呼び、うつ状態やストレス反応の軽減に有効とされています。
比較ではなく、自分たちのペースを基準にする
他の家庭やSNSの情報と比較してしまうと、焦りと無力感が生まれやすくなります。家庭ごとに背景も子どもの特性も異なるため、「昨日より少し前向きになれたか」を軸に見るよう意識しましょう。
また、「登校する=成功」「登校できない=失敗」という二分法的な見方をやめ、「今は休息の時期」「家庭での学びも成長の一部」と捉えると、親の気持ちも落ち着きやすくなります。
目標を小さく、行動を具体的に設定する
大きな目標を立てると、未達による失望感が増えます。そこで、「勉強を進める」ではなく「10分だけテキストを開く」「明日は1回だけ外に出る」といった小さな行動目標を設定しましょう。
行動心理学では、このように達成可能な目標を積み重ねることが「成功体験の再構築」と呼ばれ、自己肯定感の回復に有効だとされています。
達成できなくても責めない、「行動を起こそうとした」こと自体を評価する姿勢が、挑戦を継続する力になります。
相談先の選び方と活用法

不登校の問題は、家庭だけで抱え込むと時間とともに負担が増していきます。そこで、「誰に、いつ、何を相談するか」を早めに整理して外部の専門機関を上手に活用することが、回復と再スタートへの近道です。
相談の目的は「解決」ではなく、「支援の糸口を見つけること」です。この小さな一歩を早期に踏み出せるほど、家庭全体の疲弊を防げる可能性が上がります。
外部への相談を効果的に行うためには、「子どもの状態」と「家庭の困りごと」を分けて書き出すことが大切です。事前にA4用紙1枚ほどのメモをまとめておくと、限られた相談時間を有効に使えます。
| 相談の種類 | 相談内容の例 |
|---|---|
| 子どもの様子 | 睡眠・食事・会話・体調の変化 |
| 学校との関係 | 担任・カウンセラーとのやり取り、登校の状況 |
| 親の困りごと | 疲労感、対応の迷い、家族の関係性 |
こうした情報を簡潔に整理しておくことで、相談員やカウンセラーが全体像を把握しやすくなり、適切な助言や支援につながります。
以下に、主な相談先とその特徴について簡単に紹介していきます。
| 窓口 | 主な支援 | 費用目安 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 学校(担任・スクールカウンセラー) | 校内調整、出席や評価の扱い、面談 | 無料 | 校内での配慮や学習計画を相談したい |
| 教育支援センター・適応指導教室 | 居場所提供、学習支援、学校との連携 | 無料〜低額 | 学校外の安心できる場を探したい |
| フリースクール・通信制サポート校 | 個別学習、居場所、進路支援 | 施設により異なる | 学びを継続しながら通学負担を減らしたい |
| 医療機関(小児科・心療内科など) | 診察、治療、診断書発行 | 保険適用あり | 眠れない・食欲がないなど身体症状がある |
| 親の会・民間カウンセリング | 経験共有、心理的サポート | 団体により異なる | 同じ立場の親と話して安心したい |
(出典:文部科学省「文部科学省における不登校児童生徒への支援施策」)
相談後の行動を整理する
相談を終えたら、次に「どこまで動くか」を明確に線引きしましょう。一度に全てを変えようとすると、親子ともに疲弊してしまうからです。
行動計画は、以下のように「小さく区切る」のがポイントです。
- 来週は教育支援センターの見学だけ行う
- 今月はカウンセリング予約を取るだけにする
- 個別指導を1回だけ体験してみる
このようにステップを細分化すると、継続しやすくて結果的に回復のペースが安定します。
また、相談内容や次の予定を家族で共有するために、冷蔵庫やカレンダーにメモを貼っておくと、「今どこまで進んでいるか」が一目で分かります。
伴走してくれる支援者とつながる
不登校支援の専門家は、「答えを出す人」ではなく、「一緒に考え、支える伴走者」です。家庭内の努力だけで解決できないことも多いからこそ、第三者の視点や専門知識を借りることが、親子の回復を早める近道になります。
完璧な対応を求めるのではなく、「安心して話せる場所」として相談先を活用していくことが、心の整理と行動の継続につながります。
外部の支援機関や個別指導をチームとして取り入れることで、「孤立から伴走へ」と家庭の流れが変わり始めることでしょう。
不登校専門の個別指導という選択肢

学びの遅れや進路への不安を抱える家庭にとって、「不登校専門の個別指導」を取り入れることは、現実的な支援策としておすすめです。
「不登校専門の個別指導」は、従来の学習塾とは異なり、不登校特有の心理的ハードルや生活リズムを理解した上で、「学習支援」と「メンタルケア」を一体的に提供しているのが特徴です。
特に近年は、在宅でも支援を受けられるオンライン型が増え、通塾が難しい子どもにも柔軟に対応できるようになっています。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| キズキ教育塾 | 不登校・高校中退などに対応する完全1対1の担任制。110分授業で、通塾・オンラインを自由に選択可能。学び直しと進路支援を一体化し、大学受験・定時制・通信制進学まで幅広く対応。 |
| ティントル | 不登校専門のオンライン個別指導。30分単位で授業を設計でき、録画による復習機能も備える。講師と専任サポートチームが連携し、学習支援とメンタルケアを両立する仕組み。 |
これらのサービスでは、本人のペースに合わせたカリキュラムが設計されるため、焦らずに「学び直し」と「社会的接点の回復」を同時に進められます。
また、保護者に対しても定期面談やカウンセリングが用意されており、親子の両輪で支援が進む点が大きな強みです。
このような個別支援を早期に導入することで、学習の遅れや自信喪失を最小限に抑え、長期化リスクを防ぐことができます。
不登校期間が続くほど家庭だけでの対応は難しくなるため、「早めに専門家をチームに加える」ことが重要な戦略であることを理解しておきましょう。
不登校でも大丈夫な理由を整理

不登校という状態は、一時的に学びの形が変わるだけで、人生の道が閉ざされるものではありません。
近年では、多様な教育制度や社会的支援が整備されており、従来の「毎日学校に通うこと」だけが成長や成功の指標ではなくなっているからです。
子どもが不登校ということで「焦り」や「不安」を抱く保護者も多いですが、制度的にも社会的にも子どもが自分のペースで学び直す環境が確立されつつあります。
義務教育では「出席日数」だけで将来は決まらない
義務教育の段階では、学校への出席日数が成績や進学の唯一の基準ではありません。
文部科学省の方針でも、「不登校は問題行動ではなく、どの子にも起こりうること」と明確に位置づけられ、学校以外での学びも柔軟に認められるようになっています。(出典:文部科学省「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」)
また、出席扱いの特例制度を利用すれば、フリースクールやオンライン学習を学校外で行っても、条件を満たせば出席として認定される場合があります。
この制度により、学校に戻れなくても「学びを止めない」形で次のステップにつなげられます。
高校以降の学びには複数のルートがある
高校進学以降は、全日制以外にも、定時制・通信制・高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)など、多様な道があります。
| 選択肢 | 詳細 |
|---|---|
| 定時制高校 | 夕方〜夜間に通学する仕組みで、日中の時間を自分のペースで活用できる |
| 通信制高校 | レポート提出とスクーリング(面接指導)で単位を取得できる。家庭中心の生活でも学びが継続可能 |
| 高卒認定試験 | 高校に通わずとも、合格すれば大学や専門学校への進学資格が得られる |
これらの仕組みを活用すれば、学びを中断することなく、自分のリズムに合わせて学力や進路を形成することができます。
実際、文部科学省の統計によると、通信制高校に在籍する生徒数は近年増加傾向にあり、2023年度時点で約26万人が在籍しています。(出典:文部科学省「学校基本調査」)これは、個々の事情に応じた学び方が社会的に定着している証拠です。
学校以外の「学び」や「体験」も力になる
学びは学校の中だけで完結するものではありません。近年では、オンライン教材や動画講座、NPOによる探究型学習プログラム、地域ボランティアなど、学びの機会は多様化しています。
特に、オンライン教材(例:NHK for Schoolやスタディサプリなど)を活用することで、自分のペースで学習を続けることが可能です。
一人だけで学習を継続させることが難しい場合には、不登校専門の個別指導(キズキ教育塾、ティントル)を利用すると、あなたのペースに合わせたマンツーマンでの個別指導が受けられます。
また、地域活動や社会参加の小さな経験を積むことで、自己効力感(「自分にもできる」という感覚)が回復しやすくなります。心理学的にも、達成体験は回復期のモチベーション維持に大きく寄与するとされています。
「不登校=終わり」ではなく「新しい選択の始まり」
不登校は、これまでのやり方や環境が合わなかったというサインであり、子どもが「生きづらさ」を自分なりに示している行動でもあります。つまり、不登校の期間を通じて、自分に合うペース・人間関係・環境を見つけることができるでしょう。
今の時代は「やり直しのルート」がいくつも用意されており、遅れても、回り道をしても、最終的に自分に合う学びや働き方が選べます。
したがって、不登校は将来を閉ざす出来事ではなく、「より自分に合った生き方を模索する過程」として捉え直すことが大切です。
焦らず、時間を味方につけながら、家庭全体でゆっくりと回復と再出発を支えていきましょう。
不登校の親がしんどい時は自分を守る
- 不登校は将来を閉ざさず回復の時間だと捉える
- 親が元気でいることは子どもの安心の土台になる
- 一日に一度は五分だけでも休む時間を確保する
- 連絡と面談の頻度を決め負担を固定化しない
- 家事と学校対応は家族で交代制にして偏りを防ぐ
- 夜間は呼吸法と明るい部屋で不安をやり過ごす
- やめることリストを作り頑張らない範囲を決める
- できたことメモで自責のループから距離を取る
- 高校生の学び方は複数あり無理のない道を選ぶ
- 相談先は得意分野で使い分け予約を習慣化する
- 医療機関には睡眠食欲の変化を具体的に伝える
- 比較ではなく家庭のペースを基準にものさしを持つ
- 今日やらないことを先に決めて余白を確保する
- 目標は小さく行動は具体的に設定して継続する
- 母親ばかりにならない仕組みを家族で設計する
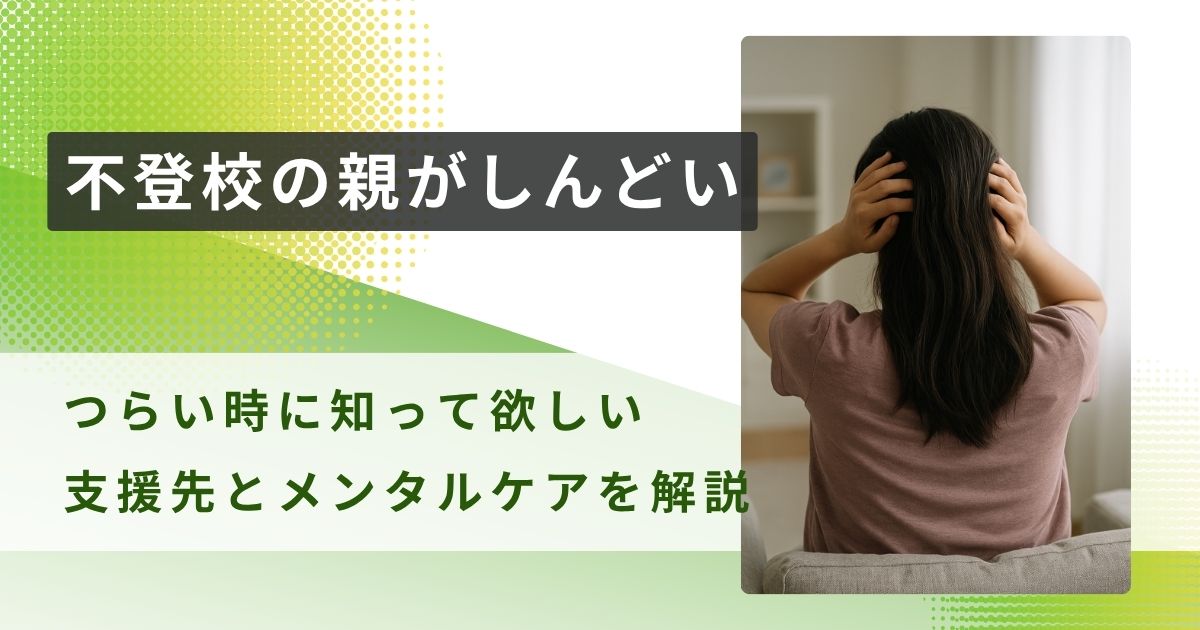

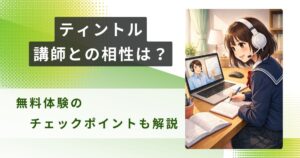
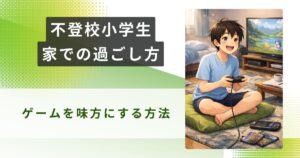
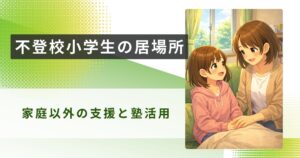
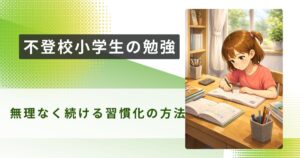
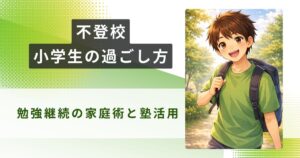
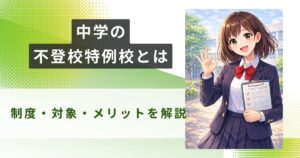
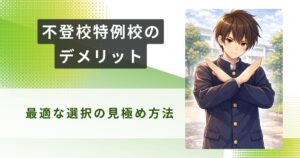
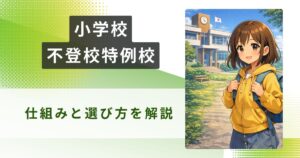
コメント